2025年度 大蔵谷ヒューマンサイエンスカフェ「二見にあった二つの紡績工場のことー播磨地方の木綿づくりの系譜―」が行われました

2025年11月9日(日)午後1時から明石市立西部図書館にて、地域研究センターの主催する一般向け講演会『大蔵谷ヒューマンサイエンスカフェ2025』が実施されました。
今回は、人文学部の矢嶋巌教授がかつて二見地区にあった二つの紡績工場の変遷について講演を行いました。
矢嶋教授は最初に、「地域における自然環境と人々の暮らしについて、ある場所が今の姿になった経緯を探り、将来を考えるための材料を掲示するのが地理学の仕事」と説明し、会場に集まった近隣地域住民の皆さんの期待も高まりました。

会場の様子(満員御礼!)
二見地域には、かつて土山駅の南に東洋紡績明石工場(旧二見工場)、東二見駅の近くに播磨重布(東洋紡績東二見工場)という紡績工場がありました。
近世の播磨地方はワタ栽培が盛んで、明治初期には印南・加古郡は兵庫県のワタ栽培の25%を占め、加古川流域の木綿は「長束木綿」と呼ばれてブランド化されていたといいます。
明治10年代、外国綿の輸入が始まったため、播磨地域では綿作が衰退しますが、紡績や織物業は外国綿を利用して発展しました。
加古川地域では栽培~織製まで一貫生産するスタイルだったため、急速な衰退に見舞われましたが、現在の西脇周辺では輸入糸による織物生産が「播州織」へと発展していきました。播磨地方の木綿の代表といえば、江戸時代は姫路木綿の白木綿であったものが、明治時代には縞木綿へと変化したのです。
1930年代には円安基調もあり、日本の綿製品輸出が世界1位になります。
1936年に建設された琴浦紡績二見工場はタイヤコードを生産し、1939年には多角化を目指していた東洋紡績に買収されて二見工場となりました。戦後は東洋紡績二見工場としてタイヤコードなどを生産し、1964 年には明石工場に改称して1979年まで操業しました。
1918年に東二見に創設された播磨帆布は、日中戦争勃発後に原料調達が難しくなったことから東洋紡績系列の東洋染色に合併され、その後重布生産量が日本一の工場になりました。第二次世界大戦末期には東洋紡績に賃借され、終戦まで東二見工場として重布生産が続けられ、軍需用繊維製品の製造も担いました。この工場は、戦後も東洋紡績東二見工場として生産が続けられ、1959年からは東洋紡績系列の播磨重布工場として1994 年まで操業しました。
第二次世界大戦末期、後の東洋紡績明石工場は、繊維生産ができなくなり、川崎航空機工業の工場に使用されました。また、後の播磨重布は東洋紡績系列となり、重布生産を継続しながら、軍用繊維製品を生産しました。それらは矢嶋教授により「忘れてはならない地域の歴史」として語られました。
戦後は民需復活、新規業者の参入により1951年綿製品輸出は世界1位になります。高度経済成長期には、2工場ともタイヤコードや重布、重布生産で発展します。
しかし、第一次オイルショックによる大打撃、平成不況により綿製品企業の多くが撤退し、東洋紡績明石工場も脱繊維をめざしますが、構造不況下で本社が工場を廃止しました。また、播磨重布はプラザ合意以降の円高進展の下で本社が撤退方針を示し、バブル崩壊後に工場が廃止されました。

『角川地名大辞典』を紹介する矢嶋教授
現在、東洋紡明石工場の跡地は種々商業施設が変遷を経て、現在では衣料品、食料品、百均、ボーリング場などになっています。
二見地区の人口増加・都市化を背景に戸建て・集合住宅開発があり、空地の時期もあったのですが、バブル経済下で、戸建て住宅開発、マンション計画、バブル末期以降はマンション建設が進展しました。一方、1991年以降は大規模商業施設の進出と撤退が繰り返され、現在に至ります。
一方、播磨重布の跡地は、バブル崩壊後の平成不況下、段階的に住宅地化していきました。こうして二見地区の木綿づくりの系譜は消滅しました。
講演後、会場からは様々な質問が挙がりました。中でも、「母親が東洋紡明石工場に勤めていた」と語ってくださった女性は、二見の中学に講堂がなかったことから、「入学式や卒業式は東洋紡の講堂を使わせてもらった。テニスコートや映画館、大きな舞台もあって、演芸も見られた」と、企業城下町ならではの貴重な話を聞かせてくださいました。
また、昭和45年頃にお姉様が二見工場に勤めていたという男性は当時、「多くの女工さんが働いていた」ことや「中の食堂もすごく大きかった」と子どもの頃のお話を聞かせてくださいました。
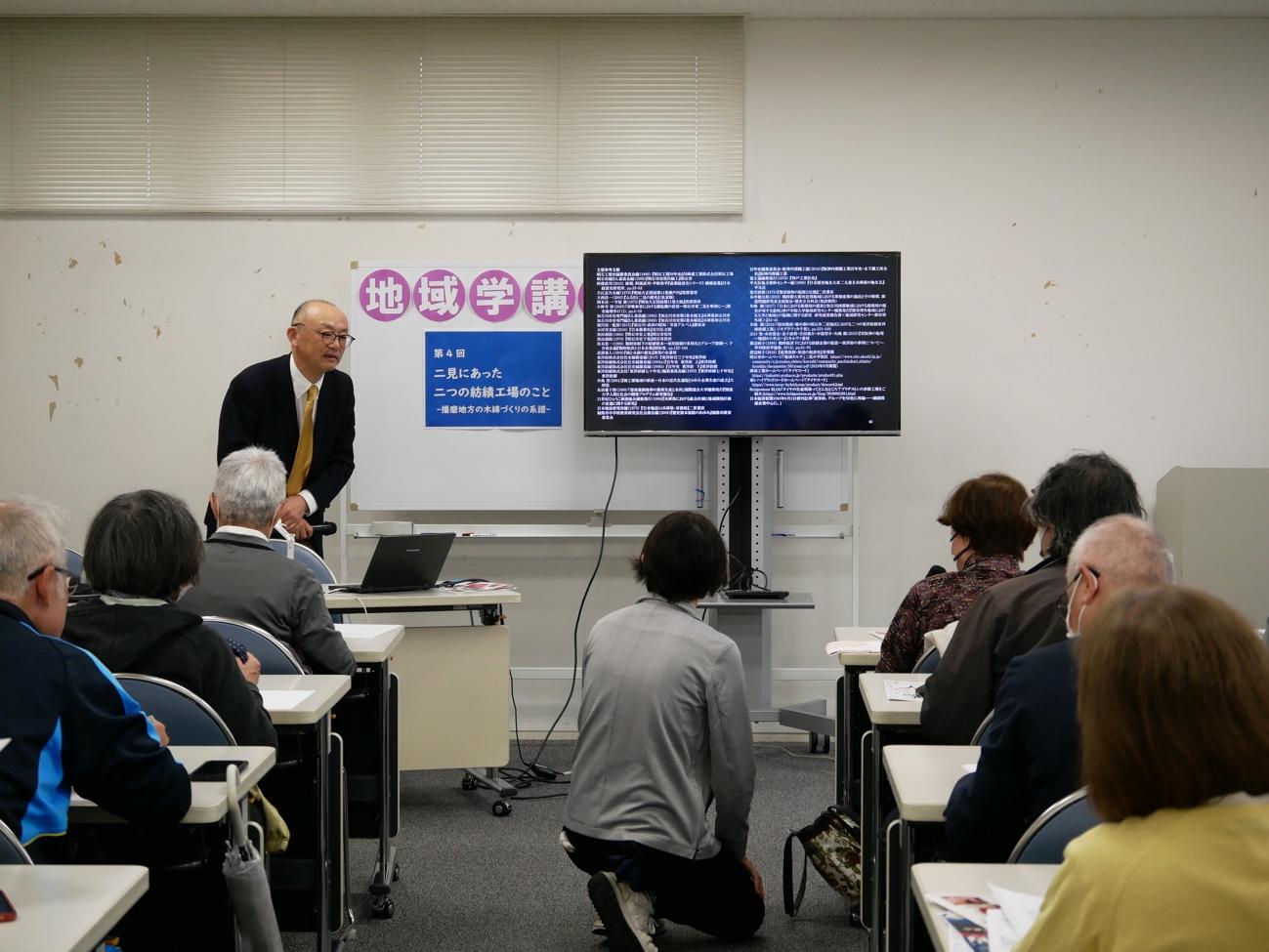
会場からの質問風景
会場からの貴重なお話(証言)に矢嶋教授も深く関心を抱き、終了後には、「またお話を聞かせてください」と、講演者が来場者に話を聞きに行くという、地域の方々との新しいつながりが生まれました。
***
地域研究センターでは、地域研究・社会貢献の一環として『大蔵谷ヒューマンサイエンスカフェ』を継続的に行っています。
次回は11月19日(水)午後6時から、人文学部の曽我部愛准教授による講演「中世の巌島参詣と瀬戸内海交通―平氏一門の巌島信仰を中心に―」を実施する予定です。ふるってご参加ください(予約、事前申し込み不要)。
写真:白方 佳果
文責:金 益見

